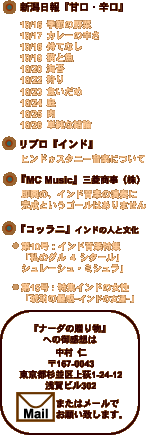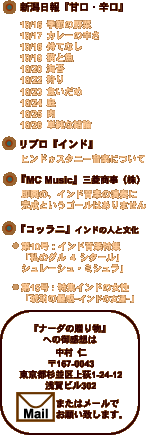|
-季節の野菜-◆1990年10月16日掲載
インドの田舎町で1973年から1983年まで十年暮らした。
最初のころは食糧事情もあまりよくなかった。
六月から九月にかけて雨期となり、野菜もほとんど出回らなくなる。
ジャガ芋、タマネギ、ナスくらいのものか?
それを毎日カレーにして食べる。毎日毎日同じものばかりだ。
栄養価が低いから量を食べなければならない。
やがて十月となり雨期が明け、緑色野菜が出回り始める。
トマト、キュウリ、キャベツなど...、
それで季節感を知る日々だった。
現在、事情は随分とよくなり、ほとんど一年中野菜が出回るようになった。
しかし便利になったが、何かをなくしてしまったような気がする。
といって、もう一度その時代に帰りたいかというと、そうでもない。人とは勝手なものだ。
今、日本で人間のワガママにかろうじて抵抗しているのは
ミョウガだけのようだ。
|

|
-カレーの辛さ-◆1990年10月17日掲載
カレーというのは簡単に言えば香辛料の煮込み物だ。
私は料理としてさほど高い評価をしていない。
インドでは裕福な家庭は高価で多種の香辛料を、
貧しい家はニンニクとトウガラシくらいで、
カレーにもピンからキリまである。
けれども彼らにとってはカレーとは日本人の味噌や醤油以上に
大切なもののように思われる。
「カレーは辛いでしょ」と尋ねる人があまりに多いので驚くが、
インド人だって辛いのが好みじゃない人も多い。
要は家庭料理だから多種多様なのである。
家庭の好みに味付けされる。
日本に帰って来てから何やらの激辛ブーム、
十倍、五十倍に挑戦と無意味な辛さを競うが、
基本的に食べ物をおもちゃにしていないか?
カレーの辛さは風土上の必然性があり、
その民族の知恵でもあるのに...。
|