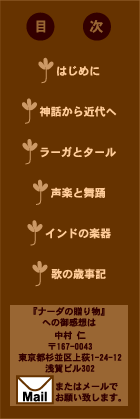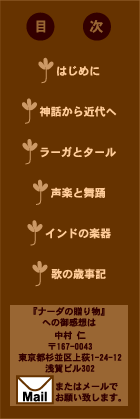|
 ンドではどんな楽器をあやつるよりも魂の宿る人間の肉体から発せられる音を聖なるものと認識し、声楽を音楽の最高位につけた。
ンドではどんな楽器をあやつるよりも魂の宿る人間の肉体から発せられる音を聖なるものと認識し、声楽を音楽の最高位につけた。
その声楽には数多くの種類がある。
インド古来の純粋な様式であるドルッパッド(Dhrupad)、ペルシャの影響を強く受けたケヤール(Kheyal)、
そして官能的で華麗な恋愛歌トゥムリ(Thumri)。これらが北インドの声楽の主流である。
また14拍のタールでうたわれるダマール(Dhamar)、外国人であったターンセンが言葉のハンディのために発案したとも言われる、
意味のない音節だけでうたわれるタラーナ(Tarana)、ウルドゥ語でうたわれる甘い抒情歌ガザール(Ghazal)などがある。
それぞれの曲には特有の感情定義があり、それをノーバ・ラサ(Noba Rasa=九つの感情)と言う。
ハシヤ(Hasya=笑い)
カルナ(Karuna=哀しみ)
ラウドラ(Raudra=怒り)
ヴィーラ(Veera=勇気)
スリンガラ(Sringara=官能)
バヤナカ(Bhayanaka=怖れ)
ビーバッツア(Beebhatsa=嫌悪)
アドブタ(Adbhuta=驚き)
サンタ(Santa=平和) 以上の9つである。
人々の生活に密着している宗教音楽の場合もこの国にはヒンドゥ教、イスラム教、仏教、
その他さまざまな宗教が地理的、歴史的に入りくんでいるが、主体となるのは声楽である。
神を讃える讃歌というものは、その旋律よりも表現媒体としての言葉の方が重視される。
ヒンドゥならばバジャン、イスラムならばカッワリー、とそれぞれ讃える神は違っても大勢の人が集い、
神への憧れと忠誠を誓い、うたいながら次第に恍惚となってゆくその情熱とエネルギーは質的に同等のものであろう。
石造りの寺に集まる人々は輪を描くように座りこみ、これから行なわれる神聖な儀式の幕開きを待つ。
ひとりのリーダーがおもむろに静かに一節をうたい始める。それは呪文を唱えるように重々しく、
敬虎な雰囲気に満ち溢れ、次第に歌は彩をおび、華麗になってゆく。タブラが一定のリズムを刻み始める。
それはたいてい軽やかで速く調子のよいものである。
また違う一節をリーダーがうたう。そのフレーズを追うようにまわりの人々は歌に参加する。
次の一節は前よりも少しばかりきらびやかで、緊張感の高いものになる。リーダーの唱える一節をまだ人々は追いかける。
こうして人々はリーダーに巧みに扇動され、声を張り上げてうたい、神の名を唱え、神の徳を讃え、
自らを歌の大洋の中に投じ、天に導かれることを祈る。夜ふけまでも夜明けまでもそれは続く。
それがカッワリーと呼ばれるイスラムの宗教歌であっても、音楽の効果と目的とするところは本質的には同じである。
古典音楽がどちらかと言えば、限られた上流階級の人々のための洗練され趣向をこらした音楽とすれば、
宗教歌はすべての人々に平等に与えられた音楽である。歌が宗教を支えてきたのか、宗教が歌を支えてきたのか
−この大地の神様はけっこう陽気な性格だったにちがいない。
舞踊もまた創造の最たる源とされ、大切にされる。
おそらく舞踊は人類が発案した最も古いパフォーマンスであろう。
モヘンジョダロから出土した踊る女人像は小さいながらもエネルギーが体全体に充満していて、
驚くほどの躍動感を見る者に与える。
またエローラ、アジャンタなどの石窟の壁画にも豊満な天女たちが舞い、踊る姿がいたる所に見られる。
古代のヒンドゥ教の寺院の壁面には創造の化身であるシヴァや太鼓やシンバルを持って踊る女たちの群像が
所狭しと彫られている。
タントラ派の影響を受けた中世の中央インドにはカジュラホやブバネシュワールに代表される石院が建設され、
官能的なミトゥナ像に混じって自由奔放に乱舞する像がレリーフとして上部の方まで壁面をうめている。
これに最近非常に評価を得てきているオリッサ州のオリッシィ・ダンス(Orissi)を加えて、
五大舞踊と呼んでいる。
古典舞踊はそれぞれ寺院や宮廷という強大な権力に支えられ庇護されてきたものであり、
踊り手たちは一種の巫女の役割りをすることもあった。それらの専業の踊り手によって古典舞踊は高度に発展してきたのである。
インドにはその他、土着的な性格の強い少数民族の踊りやさまざまな祭りで披露される大衆的な踊り、
またタゴール・ダンスに代表される近代的センスを持つ舞踊、あるいは西洋の影響を受けた舞踊劇等、
多種多様なものがある。
各地の各民族に伝えられてきた独自の踊りも、大切に伝承されてきた。
セライケラやプルーリヤの仮面劇チョウ・ダンス、あるいは南インドのクチプリなどは、その代表的なものである。
それぞれの基本的な技術や起源は異なるが、おおむね共通しているのがインド独特のリズム感、ムードラという手の仕草、
また「ラーマヤーナ」や「マハバーラタ」を原典とする物語である。
このように舞踊も古く、奥ゆきの深い歴史を持つが、前述のオリッシィ・ダンスは11世紀にイスラム教徒の侵入により
寺院が破壊され、今世紀に至るまでその存在を無視されていたものがコナラックの太陽寺院のレリーフから復元されたものである。
舞踊はいつの時代にも強い生命力を持っている。
音楽と音とは切り離せないものであるが、音というものを考える時、
古来インドの賢者たちはいくつかの定義を示してきた。
器官を通して知覚できる音と、そうでない音
― つまり心の中に直接聞こえてくる音 ― があり、前者をアハート(Ahat)、後者をアナハ―ト(Anahat)とした。
そしてアハートには2種類あり、それは音楽的な音ナーダ(Naada)と単なる雑音とである。
ここでその定義を多少私なりに解釈し、アナハートなるナーダというものを考えてみた。
それは器官を通して聞く事のできるナーダとはまた別に、心の中に直接触れる音楽的な音、
あるいは天から降りしきるさらさらとした光の雨のように、私たちの心の中に積もりゆく聖なる音ではないだろうか。
それは楽器の響きでも声帯を通してうたう歌でもなく、静寂の中に居ても呼びかけてくる、
清らかで不思議な音として存在してはいないだろうか。それは自らの心の中に生まれてくる最も純粋な音楽として、
あるいはこの天空のどこからか語りかけてくるひとつの意志、あるいは善意を知る唯一のものではないだろうか。
音楽家はより正確により美しく、劇的に自分の演奏を試みる。
しかしアハートとしてのナーダはいずれアナハートとしてのナーダに移りゆき、
徐々に光や風の存在に近づいてゆくのではないだろうか。
老いて死にゆく音楽家の心の中には天の声としてのナーダがきらめきながら降りしきっているのではないだろうか。
少なくとも私はそう信じている。
|