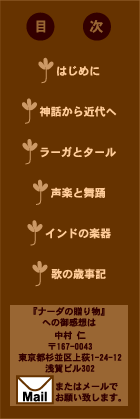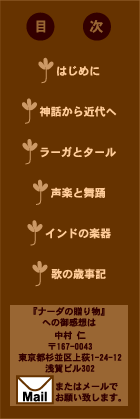sarinda |
 口にインド音楽といっても、
古典から宗教音楽、映画音楽、祭りの歌、労働歌、大道芸人の音楽、少数民族の歌と
様々なものがある。その目的、技法、対象もそれに則したものになり、それによって使用される楽器も用途にかなう
ように発案されてきた。 口にインド音楽といっても、
古典から宗教音楽、映画音楽、祭りの歌、労働歌、大道芸人の音楽、少数民族の歌と
様々なものがある。その目的、技法、対象もそれに則したものになり、それによって使用される楽器も用途にかなう
ように発案されてきた。
 shehnai |
弓奏楽器ではサーランギ、ディルルバ、イスラジ、サリンダー、
撥絃楽器にはシタール、サロッド、ヴィーナ、ビーン、スルバハール、
吹奏楽器は素材としては木、竹、またはアシや角や骨、ほら貝のたぐいまで様々であるが、
大きく分けて婚礼の儀式に使用されるシャーナイに代表されるリード楽器、
そしてクリシュナの重要な小道具であるバンスリーに代表される横笛がある。
インドはまた打楽器の宝庫でもある。
一般的には木製か粘土製のボディに皮を張った太鼓のたぐいが代表的なものだが、
その使用目的や作られた年代によって形が微妙に異なり、すべての打楽器を挙げる事は不可能に近い。
 mridangam |
ヴェーダの時代からその名を明記されているムリダンガム、
北インドでの古典声楽の伴奏に使われているパッカワージ、そしてタブラ、コール、ドール、ドーラックなどがあるが、
それぞれ音質も異なり、演奏技法もそれぞれ工夫が凝らされている。
 dhol |
太鼓の他にシンバルや鈴、鉦のたぐいを数え挙げていけば、それらを統括するのは困難になってしまう。
なにしろ祭りの夜の興奮した民衆にとってはバケツもナベも立派な楽器となってしまうお国柄なのである。
ここでいくつかの代表的な楽器を紹介してみよう。
シタールは本来ペルシャの楽器であったが、イスラム教徒の侵入後、
十三世紀にインドにもたらされたものである。原型は三本絃のまことに素朴なものであったらしいが、
その紹介者であり自らも偉大な音楽家でもあったアミールクスローが改良の手を加えていったと言われる。
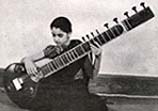 Sitar |
それから今日に至るまで様々な人々の創造的なアイディアが加えられて現在の形に至ったが、
ピアノやヴァイオリンのように、これ以上改善の余地がないほど完成度の高い楽器であると言われている。
絃は二段になっていて、上段には七本、下段には十一本から十三本の共鳴絃が張られている。
上段の七本の絃は主旋律絃、基調音絃、低音部のドローン効果を果たす二本の絃、そして細い三本のリズム絃(チカリ)、
というように簡単な形ではあるが、メロディ、ハーモニー、リズムの三役を一台の楽器で表現できるように作られている。
フレットは可動式で半音やマイクロトーンの演奏の為に棹の前後に移動できるようになっている。
インド音楽の性質上高度な和音構成はないがその代わり、
フレットの位置での音階と絃をフレットに沿って横に引っ張って作る音階(ミーンド)の
二種類の技法がシタールの最大の特徴である。
また象牙、あるいは鹿の骨で出来たブリッジには神技と言ってもよいほど微妙なカーヴが付けられていて、
その為に絃とブリッジの接点の振動を変える事によって生じる音(ジュワリ)を作り出す事ができ、
これがシタールを単なるスチール絃の絃楽器から区別して、いっそう深い複雑な音色を出す楽器とする事に大きく寄与している。
実際シタールの維持で一番重要な事はそのかすかな隙間をいかに保つかという事であり、
楽器職人の腕と評価はそれだけで決まると言っても過言ではない。
また本来、絃楽器には絹糸か動物の腸を縒った絃(ガット)が主として使用されてきたが、
工業の発達により銅や鋼鉄製の絃が使用されるようになった。その結果、この一世紀の間に絃楽器の伝統的な音色というものは
大幅に変化してきた。
またその素材の品質の向上により、元来の絃では不可能だった演奏法や表現が可能になったのも事実であろう。
 tanpura |
タンプーラはまことにもって単純な楽器である。
一本の棹に下部には冬瓜のたぐいで作った共鳴胴を取り付け、その上に通常四本の開放絃が張られる。
それはフレットもなければ弓で奏く訳でもない。ただ開放絃を指で弾くだけであり、
一見演奏技術も音楽性も必要ないかのように見える。
しかしタンプーラはこの楽器のピッチが調絃の際の基本音となるという、重要な役目を担っている。
演奏者は自分の楽器の調子が外れた場合、この音を聞きながら正しいピッチに調絃し直す事ができるし、
声楽家は自分の基調音を常に知る事ができる。
この基本音となる事以上に重要なタンプーラの役目はドローン(通奏低音)を常に維持している事である。
四本の絃はPa・Sa Sa Sa・(ソ ド ド ド・)のだいたい一度、五度の和音関係でしかないが、この音が演奏の間中流れていて、
ひとつの音のスクリーンを作っている。
この上にきらびやかなメロディが繰り広げられてゆくのであるが、ドローンがバックに流れている事によって音域の広がりと安定感を生み、
そして一種独特の雰囲気を醸し出す事ができる。
この楽器もシタールと同じようにブリッジにジュワリが施され、絃とブリッジの間のかすかな隙間を糸をはさむ事で操作する。
その為に細かなヴァイブレーションが増幅され、一種「さび」のきいた持続音が作り出されるのである。
このドローン効果とジュワリはインド音楽界の偉大な発見のひとつであろう。
イスラジはサーランギやサリンダーと同じような弓奏楽器であるが、
インドでもあまり知られていない楽器のひとつである。
現在の構造は棹の部分はシタールとほぼ同じで、それをいくぶん小型にしたものである。
胴の部分は楕円形で、その中央両側に弓を置くくぼみがある。
 esraj |
非常に似た楽器にディルルバがあるがこれとの相違点はディルルバの胴が台形であるという事だけである。
イスラジがベンガル地方を中心に演奏されるのに対して、ディルババはインド西部が中心である。
もともと同じ起源を持つ楽器と言われているが、それはあまり定かではないようだ。
イスラジの場合、文献を歴史的に遡っていっても、はっきりしているのはせいぜい二百年ほど前までで、それ以上は正体不明である。
本来は土着の歌の伴奏に使われていた程度のあまり地位の高くない楽器であったが、
この四十年ほどの間にいろいろと多くの改良が加えられ演奏法が変わり、
そして偉大な演奏者が生まれた事などがあって最近になって注目を浴びるようになった。
本来の形ではフレットが現在の半分程の数しかなかったが、シタールと同じように半音単位のフレットが組み込まれた。
また弓の質も改良され、毛は馬のしっぽ、長さも充分に長くなった。そして最大の変化は演奏スタイルで、
今まで坐って棹を肩にかけて演奏していたのを楽器を垂直に立たせた事である。
これによって右手の弓の速度、左手の絃上の移動とその速度等今まで演奏を制約していたものから自由になり、
音楽的な可能性がいっそう膨らんだ。さらに古典音楽の理論と技術を熟知した演奏家が出現し、
今まで一地域の民族楽器だったものを古典楽器の地位にまで昇格させる事に成功したのである。
しかしまだ楽器の構造上統一されたものはなく、絃が四本だったり六本だったり、共鳴絃が何本か何本か多かったりというように
演奏家と楽器職人がそれぞれのアイディアを持ち寄り、独自の工夫を凝らしたものが作られている。
音楽的には成功したものとそうでないものとがあり、現在完成された形へ向けて自然淘汰の途上にあると言える。
考えてみるとインド楽器の中には定型というものがなく、あれだけ完成されたシタールにしても、ある人は六本絃、
またある人は独自の必要性から八本絃にする事もあり、派手な装飾的彫刻を好む者も、まったく装飾のないのっぺりした楽器を好む者もいる。
また音質もシタールらしさという事においては共通しているが、個々の楽器の音色はまことに個性的で変化に富んでいる。
タンプーラなどはそのサイズもまちまちで特定のサイズというものがなく、職人の気分次第というところが本当のところではないだろうか。
本来四絃であったものが五絃であったり六絃であったりする。その辺はまことに大らかなもので、
使用目的に支障を来さなければよいとする消極的態度の職人から、
これぞ私の一大発明と言わんばかりに誇らしげで積極的なアイディアを加える職人までまちまちである。
現に街の楽器屋通りをぶらついてみると、倉庫の中に共鳴絃の付いたギターやら馬の首の彫刻を施したシタールやら、
何やら得体の知れぬ楽器が埃の中に積み上げられているのを目にする。
現在我々が完成品とみなすそれぞれの楽器の過去の経過もこれと似たりよったりで、いろいろな試みがなされたその結果として、
多くのものが闇に葬られた中でいくつかの楽器がかろうじて生き残って現在に至ったものであろう。
 tabla |
北インドを代表するタブラもまた、その栄光を勝ち得てきたもののひとつである。
原型はパッカワージと呼ばれる、現在では最古の古典声楽ドゥルッパッドの伴奏に使用されるシリンダー型の両面太鼓であった。
それを中央で切り離し、二台の太鼓としたところからタブラの歴史は始まる。
右手で打つ高音域の太鼓は気をくり抜いたもので、それひとつだけでもタブラと呼ばれる。
左手で打つ方は以前は素焼きの半球体の壷形のものだったが、今は銅製のボディの上に山羊の皮を張ったもので低音域を受け持ち、
バンヤ(「左」の意)と呼ばれる。そして二台で一組となり、その総称がタブラである。
 pakhawaj |
タブラの最大の特長は皮の表面のガブと呼ばれる黒い部分である。
これは砂鉄(あるいはマンガン)と米粉を練り合わせて同心円上に五重、六重に塗り重ねていったもので、
そのためにバンヤの方ではその容積の割にははるかに重厚な低音が出るし、
またタブラの方では表面の異なる部分を叩けば異なる音色が出る。
そして両方の太鼓のそれぞれの音色をかけ合わせることにより、二十種類もの音色が出せるわけである。
その異なる音色を使用しながら様々なリズム・パターンを編み出していく事によって、
タブラは単純な原始的打楽器の世界から脱出して、よりメロディ楽器に近い存在となった。
また音質のまろやかさとスピード感がある為、西洋楽器との共演も最近非常によく見られ、現在最も注目されている楽器である。
数あるインド楽器の中で最もインド的な楽器はヴィーナであろう。
今日最もポピュラーな楽器であるシタールやサロッドが本来、ペルシャ地方の外来文科であるとすれば純粋にインドに
起源を持ち発展して来た楽器はヴィーナである。
古くから文献の中にその名が見られ、音楽史上極めて重要な位置を占めてきた。
ヴィーナと言う名前は特定の楽器を指すものではなく、絃楽器一般を呼ぶ総称であった。
ほとんどの楽器がそうであったように、ヴィーナも初めは単純な構造で開放絃を並べたハープのような形であったが、
次第に棹と響鳴胴を持つリュート型のものとなり、現在の形は南インドのタンジョールで完成されたものである。
現在では木をくり抜いた桿と胴体を本体とし、その本体にかぼちゃをくり抜いて、
あるいは紙の張り子で作った共鳴体が取り付けられている。
絃はシタールと同じように七本であり、それぞれの役目はシタールとほぼ同じである。
他の楽器も長い時間をかけて形が変わってきたのであるが、
ヴィーナの場合はその長い時間の間に最初の形と現在の形とでは同一の楽器としての共通点が見つからない程、大幅に形が変わってしまった。
 veena |
インドの楽器の中では一番大型に属するものである。また今まで残されてきたヴィーナを見ても、
螺鈿や象牙をふんだんに使用した美しいものがあり、工芸品として見ても見事である。
これもまた他の楽器にはあまり例を見ないことで、この楽器が単に音楽的な機能を持った道具というものではなく、
人々から特別の敬意と愛着を持って迎えられていたという証拠を示すものであろう。
今でも南インドでは一番人気のある絃楽器である。
一概にヴィーナと言っても現在ではさまざまな名称の楽器がある。
形は少しずつ異なるが、北インドではビーン、あるいはルードラ・ヴィーナ、木製の胴の代わりにふくべを持つラサ・ヴィーナ、
孔雀の姿をしたモユル・ヴィーナ、とさまざまなものがあるが、その共通した特長はワックスで固められた可動式のフレットであり、
ミーンドを多様に取り入れた演奏法である。
インドの楽器でについてもうひとつ明記しなくてはならないのは、基本的に鍵盤楽器が存在しないという事である。
それはインド音楽の一オクターブという概念がシュルティ(マイクロトーン)の連続から成り立つ曲線のような音階であり、
西洋音楽のように半音を最小単位としないからである。
つまりインドの古典楽器に最低限必要とされる機能とは半音以下のマイクロトーンが演奏可能だという事である。
前にも述べたようにインド音楽では声楽を音楽の基本に置き、器楽曲を模倣するというところから発達してきたものであり、
いくらでもマイクロトーンの出せる人間の声の表現に技術的に可能な限り近付こうとしてきた音楽であるから、
必然的に楽器の機能もそのように改良された訳である。残念な事に鍵盤楽器ではこれができないので、
インドの音楽家たちはあまり興味を示さなかったという事なのである。

santoor |
サントゥールについてもそれが言える。
サントゥールは箱型のボディの上に金属製の絃を張り、撥で叩いて演奏するもので、
この楽器に類依したものは世界各地で見られる。
中近東のサントゥールはインドのものより少し小型であるが、楽器としての性格はほとんど同じものであり、
また中国の揚琴も同系列のものである。
サントゥールは長い間、カシミール地方の一民族楽器でしかなかったが、最近になってその演奏技術が改善された為、
より広く演奏されるようになった。またリズム感、あるいはスピード感、
そして何よりもその音色の可憐な美しさで多くの人々を魅了している。
それでサントゥールはようやく古典楽器の仲間入りを果たしたのだが、
それでも厳密な意味ではセミ・クラシック用の楽器としての地位しか与えられていないのだ。
その理由は絃を撥で叩くのみという、絶対に中間音が出ない構造になっている、というだけのものである。
最近とみに人気を集めているのがヴァイオリンとハーモニアムと呼ばれる小型の箱型のオルガンである。
ヴァイオリンは西洋からの借り物であったがインド音楽の要求する機能を満たしているので、
堂々とインドの楽器の地位を確立しており、ソロでも歌の伴奏でも鑑賞に耐えるものであり、
インドの楽器としても違和感のないものとなった。
またはなはだ言いにくい事であるが、多くのインド人がハーモニアムをインド独自の楽器だと考えているが、
これは単に西洋の楽器の模範であり、インド音楽の楽器たるべき条件をひとつも満たしていない。
左手でいわゆるふいごの役目をする蛇腹を常に押し続けなければならないから、
演奏は右手一本しか使えない。また多くても三オクターヴくらいしか音域がないから、
西洋のオルガンやピアノに較べて数段劣る。そして再三述べてきたが、鍵盤楽器の宿命上、中間音が出ないのである。
以上の事を考えると、インド音楽の中では異端子されるべきものであるが、
音程がしっかりしている、音色が重厚で何かしら通奏低音ドローンの役目をする、演奏法が簡単である、
等の理由で使用される機会も増え、年々その役割は重要になってきている。

sarangi(R) |
本来ならば古典声楽の伴奏はサーランギの役目であった。
しかしこの楽器は演奏法が極めて難しい上に、太いガット絃を指の付け根で擦るようにして
演奏するので、サーランギの奏者はその音楽性以上に肉体的条件を要求された。
つまり爪が厚いか、その苦痛に耐えられるかがまずは問われたのであった。
最近ではその苛酷な条件に耐えるよりもより安易な選択をする人々が多くなり、
サーランギ奏者の数は減少している。それにとって替ったのがハーモニアムなのである。
思えばインドの楽器はサディスティックなものと言える。
シタールは硬いスチール絃を指先で押さえる為に、初心者は音楽の喜びよりも先に
肉体の激痛に耐える事を余儀なくされ、またサロードは爪を絃に直角に立てて
スライドさせる為、爪の磨耗は激しく奏者は絶えずカルシウムの補給に走り廻っている。

sarod |
しかし多分、インド音楽の奏者達は電気の力を借りずに、自分の肉体を削りながらも
作り出す生の音をより美しく磨きあげる事に密かな誇りを感じているはずである。
今まで見てきたような高度に発達した古典楽器の他にも極めて原始的な楽器もあり、
インドの楽器は千差万別である。
大地を耕す者にとって、より身近な材料で音を楽しむのも音楽であり、
また旅芸人が持ち運びに便利でかつまた大音量の楽器を好むのも彼等の必然であり、
贅を凝らした宮廷で職業的音楽家の至高の芸を愛でるのも、人々の要求がそこにあったからである。
人々の美意識がそれを探求し、社会がそれを支え受け入れてきたのである。
|